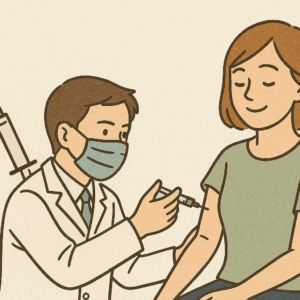バックナンバー
- 内科全般
- 内視鏡
このような症状が出たら 頭痛
カテゴリー:内科全般| 2025.12.03
頭痛の原因としては、頭の病気だけではなく、精神的なストレスや全身的な病気など様々なものが挙げられます。そのため一言に頭痛と言っても、原因によって痛みを感じる部位が異なり、「頭の表面が痛い・奥の方が痛い」「頭の一部が痛い・全体が痛い」「にぶい痛み・鋭い痛み・ズキズキするような痛み」など様々な症状として表れます。また、めまいや嘔吐などの症状を伴うこともあります。
痛みを感じる部位
以下の各組織の刺激が頭痛として感じられます。
・頭蓋骨外の皮膚・皮下組織・腱膜・筋・動脈・骨膜
・目・耳・鼻・副鼻腔
・頭蓋骨内の血管
・脳神経
頭痛の分類
頭痛は以下の種類に分類されます。
- 慢性的に繰り返して出現するもの(機能性頭痛)
・偏頭痛(血管性頭痛)
古典的なものとしては前駆症状(目がチカチカする・気分が悪い・吐き気がするなど)が出現します。ただし、前兆なく頭痛が起こる方のほうが多いです。
頭がズキズキするような痛みで吐き気や光・音・匂いなどに対する過敏症を伴うことがあります。
若年~中年の女性に多く、40%以上に家族歴がみられます。ストレスなどからの解放後に起こることが多く、女性は発作の出現と月経周期との関係も深いと言われています。
発作時は治療薬を内服した上で、なるべく刺激を避け、暗く静かな場所で安静にして、頭を冷やしましょう。
・緊張性頭痛(収縮性頭痛)
後頭部・前頭部あるいは頭全体に締め付けるような痛みが出ます。頭頸部の姿勢やストレスにより頭頸部を中心とする筋肉が持続的に収縮し(いわゆるコリ)、筋肉の血流が悪くなって痛みを感じます。夕方に強くなることが多く。吐き気や光・音への過敏症は伴いません。
ストレッチや体操などで首・肩のコリをほぐし、ストレスを回避することが重要です。
・群発性頭痛
片方の目の奥~側頭部にえぐられるような激痛発作が1時間ほど持続します。痛みは深夜に起こることが多いと言われています。1日1~
3回の発作が1~2ヶ月の間にまとまっておこります。頭痛が起こっている側で目の充血、流涙、鼻水・鼻づまりなどの症状を伴います。アルコールなどで誘発されることがあります。
- 緊急性を要する頭痛
脳出血・くも膜下出血などの脳血管障害による頭痛は早急に治療を行う必要があります。
これらの頭痛は
・これまでの人生で感じたことのないほどのひどい頭痛
・麻痺・意識障害・失語などの症状がある
・突然発症する(何をしている時に痛みが始まったか答えられる)
などの特徴があります。上記の特徴を伴うような頭痛が出現した場合には一分一秒を争う可能性がありますので、ためらわずに救急車を呼んでください。
- 頭蓋内疾患による頭痛
脳腫瘍や脳炎・髄膜炎・水頭症・硬膜下血腫などの病気は頭蓋内圧亢進(頭蓋骨の内側に腫瘍・炎症・血腫などがあることにより頭蓋内容積が増大し、神経や硬膜が引き延ばされることで痛みが出現する)により頭痛を生じます。吐き気・嘔吐を伴うことがあります。これらも迅速に治療を受けることが必要です。
・薬物の過剰摂取による頭痛
市販薬の鎮痛剤やカフェインを摂取しすぎると頭痛の原因になることがあります。
・顔面の炎症からくる頭痛
緑内障・目の炎症・眼精疲労
中耳炎・耳の腫瘍
副鼻腔炎・
虫歯
帯状疱疹(ヘルペス)
など頭以外の部位に原因がある場合もあります。
頭痛は多くの方が経験する症状ですが、中には緊急で治療が必要な場合もあります。特に突然発症した場合・麻痺や意識障害などの症状を伴う場合・これまでに経験したことがないほどの強い痛みを感じた場合はくも膜下出血などの緊急性の高い病気が原因の可能性がありますので、ためらわずに救急車を呼んでください。
このような症状が出たら – 食欲の異常
カテゴリー:内科全般| 2025.09.10
体の調子が悪い時に食欲がなくなる、ということを誰しも経験したことがあるかと思いますが、食欲は食べ物に対する生理的な欲求であり、体の健康状態と密接に関係しています。
食欲を支配する因子としては、血液中の血糖値・遊離脂肪酸・インスリンや、モチリン・グレリン・レプチンなどの消化管ホルモンが知られています。また、脳の中でも大脳皮質や視床下部という領域が食欲に関係していると言われています。
食欲異常の種類
食欲の異常というと、食欲が無くなる「食欲不振」が有名ですが、他にも様々な異常が現れることがあります。
・食欲不振
食べ物に対して食欲がわかなくなる、もしくは無くなる状態
・大食症
食欲が異常に亢進した状態。糖尿病などでみられることがある。
・異食症
氷や土など通常は食べないものを好んでたべること。一部の貧血などおこることがある。
食欲不振の原因
食欲は上に記載しているとおり、さまざまな因子が関与しているため、食欲がなくなる原因も幅広い範囲の病気が考えられます。主に、内臓によるものと内臓以外によるものに分けて考えられる原因を挙げていきます。
・内臓によるもの
がん
食道・胃・大腸などにがんができると蠕動運動や消化が悪くなり、食欲がわかなくなることがあります。また、腫瘍が大きくなった場合は食道・胃・大腸が物理的に狭くなり、食べ物が通過しづらくなったりすることがあります。診断は内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)で行います。
消化管(胃腸)以外のがん、たとえば膵臓がんや胆嚢がん、肺がん、婦人科系のがんでも病状が進行すると食欲がなくなることがあります。これを悪液質と言います。
逆流性食道炎
胃と食道のつなぎ目が緩くなり、胃から食道へ胃酸が逆流する病気です。胸焼けなどの症状が出ることが多いですが、後述する機能性でディスペプシアを合併していることも多く、食欲が出なくなることもあります。
食道カンジダ症
食道にカンジダという真菌(かびの一種)が生えることがあります。多くの場合は無症状ですが、ひどくなると食欲不振や胸のつかえ感などの症状が出ることがあります。内視鏡検査(胃カメラ)で診断し、症状がある場合は抗真菌薬で治療します。
胃炎
胃炎がひどくなると食思不振や胃痛などの症状を起こすことがあります。胃炎にもピロリ菌や薬剤によるものなど、様々な原因があります。こちらにまとめておりますので興味がある方はご参照ください。
胃潰瘍
胃潰瘍ができると胃痛などの症状が出ることが多いですが、普段から痛み止めを定期内服されている方や、糖尿病の方などは胃痛を感じず、食欲不振として症状が出ることがあります。内視鏡検査(胃カメラ)で診断し、胃酸を抑える薬や胃の粘膜を保護する薬で治療を行います。
幽門狭窄症
胃潰瘍や十二指腸潰瘍が治ったあとに粘膜がひきつれて胃や十二指腸が変形し、食べ物が通りづらくなることがあります。
機能性ディスペプシア
機能性ディスペプシアは胃の機能による問題です。潰瘍やがんなどがないにも関わらず、慢性的に胃もたれ・膨満感・みぞおちの痛み・満腹感などの症状が続き、食欲がなくなります。モチリン・グレリンなどの食欲に関与するホルモンの異常や、ピロリ菌の感染、胃の知覚過敏、ストレスや心理的な要因などが原因として挙げられますが、これらが複合的に組み合わさっていることも多くみられます。治療薬として胃の動きをよくするような薬があります。
慢性便秘症
便秘が続くとお腹が張り、食欲にも影響が出ることがあります。便秘は腸の狭窄や閉塞によっておこる「器質的便秘」と腸の蠕動運動の低下・異常による「機能性便秘」にわけられます。器質的便秘には大腸がんなど重大な結果をもたらす病気が含まれているので、「たかが便秘」と軽く考えず、一度は大腸内視鏡検査(大腸カメラ)をされることをお勧めします。
腸閉塞
腸閉塞は「イレウス」とよばれ、小腸もしくは大腸が完全に閉塞し、食べ物や便が通過できなくなる病気です。お腹の手術を行うと術後何年か経ってから小腸に癒着が起こり、腸閉塞の原因となることがあります。また、大腸癌などの癌が大きくなると腸閉塞を来すこともあります。癒着が原因の場合は入院して数日間絶食・点滴をすることで自然に解除されることもありますが、自然に解除されない場合・血管もまきこまれていて腸の血流が悪くなり壊死(腐ること)をした場合・癌が原因の場合などは手術が必要となります。
食中毒
食中毒などが原因で胃炎や腸炎が起こると、胃腸の動きが悪くなり食欲が低下します。
・内臓以外によるもの
感染症
かぜやインフルエンザなどにかかったときに食欲が出ないということはよく経験されると思います。
細菌・ウイルス感染を起こした際の全身症状のひとつとして食欲不振が出ることがあります。
腎臓や肝臓、心臓などが悪くなると、体全体がだるくなり、食欲も減退することがあります。
ストレス・神経症
ストレスや疲れなど精神的な問題が原因で食欲がなくなることがあります。
このように様々な原因による食欲が低下することがあります。中には胃がんや大腸がんなど重大な結果をもたらす病気が原因になることもありますので、食欲の低下が長期間続く場合は一度病院を受診することをお勧めします。
胃がん検診(胃カメラ)について
カテゴリー:内科全般| 2025.07.03
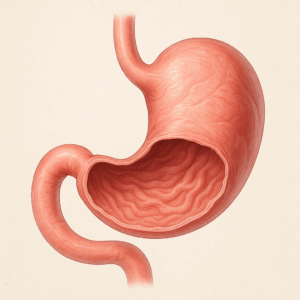 胃がんは日本で4番目に死亡者数の多いがんですが、定期的に検査を受けることによって予防や完治が可能な病気です。胃がんはピロリ菌という菌が原因となっていることが多く、ピロリ菌の除菌治療を行うことでその発生率を大きく下げることができることが知られています。また、胃がんになってしまった場合でも早期に発見できた場合は内視鏡治療で完治することができますので、手術でお腹を切らなくても治すことができます。このように定期的に検査を受けてピロリ菌の治療や胃がんの発見を早めに行うことが極めて重要です。
胃がんは日本で4番目に死亡者数の多いがんですが、定期的に検査を受けることによって予防や完治が可能な病気です。胃がんはピロリ菌という菌が原因となっていることが多く、ピロリ菌の除菌治療を行うことでその発生率を大きく下げることができることが知られています。また、胃がんになってしまった場合でも早期に発見できた場合は内視鏡治療で完治することができますので、手術でお腹を切らなくても治すことができます。このように定期的に検査を受けてピロリ菌の治療や胃がんの発見を早めに行うことが極めて重要です。
宝塚市では2024年まで血液検査による「胃がんリスク健診」というものが行われていましたが、2025年より廃止されてしましました。また、内視鏡(胃カメラ)による胃がん検診を行っている自治体もありますが、宝塚市では実施されておりません。
胃がんは早期の段階で発見できた場合は内視鏡治療でお腹を切らずに治すことができます。
当院では独自に検診の胃カメラ(内視鏡ドック)を行っております。
・検診・ドックとは?
まず普通の内視鏡検査(胃カメラ)と検診・ドックによる内視鏡検査(胃カメラ)の違いをご説明します。検査の内容は一緒なのですが、費用負担が変わってきます。一般的な診療では健康保険が適応され、自己負担は1~3割となります。一方で検診・ドックは保険が適応されないため全額自己負担により検査を行うことになります。お腹に病気がある可能性がある場合は保険の適応になりますので、過去に胃の病気をされたことがある方(胃がん・胃潰瘍・胃炎・ピロリ菌感染など)や、これまでになにかお腹の症状を自覚したことのある方(腹痛・胃もたれ・吐き気・詰まる感じがする・胃の調子が悪いなど)は保険適応で検査ができる可能性がありますので、医師にご相談ください。
また、内視鏡検査(胃カメラ)では胃の中の組織を採取して精密検査に提出する必要がある場合があります(病理検査)。検診・ドックで胃カメラを受けられた方も病理検査にかかる費用は健康保険が適応されます。
・胃がん検診は内視鏡検査(胃カメラ)が有効!
2024年まで宝塚市では血液検査による「胃がんリスク健診」というものが行われていました。これは血液検査によるものですが、胃がんの原因となるピロリ菌が胃の中にいる可能性を調べるもので、直接的にピロリ菌感染や胃がんの有無を調べるものではありませんでした。そのため「胃がんによる死亡率を下げる」という意味では有効性がはっきりせず、2024年で廃止となってしまいました。
一方で、冒頭にご説明したとおり胃がんは日本では非常に多い病気で、死亡者数は癌の中で4番目に多い病気です。胃がんリスク検診に代わる検診を市の方で実施してほしいところですが、現在そのような動きはありません。そこで当院では独自に胃カメラ(内視鏡)による検診・ドックをおこなっております。
一般的に胃がん検診にはバリウムによるものと胃カメラ(内視鏡)によるものがありますが、内視鏡検査(胃カメラ)による検診の優位性を示す報告が多数出ています。
・延べ40,620例の胃がん検診での検査法別の胃がん発見率の比率では、内視鏡検査0.28%、バリウム検査では0.04%で内視鏡検査の方が優位に胃がん発見率が高かった1)。
・胃がん検診を受けていない群は受けた群と比較して胃がん死亡率が約3倍高かった。検診を受けた群のなかでバリウム検診と内視鏡検診を比較したところ、内視鏡検査受診者の胃がん死亡はバリウム受診者に比べて優位に少なく、検診後5年以内の胃がん死亡率は約1/4だった2)。
このように胃がん検診を受けることで胃がんによる死亡率を下げることができ、またバリウム検査よりも内視鏡検査(胃カメラ)検査の方がその効果が高いことがわかっています。
特に早期の胃がんにおいいては、病変はわずかな隆起や凹み、色調の違いとしてしか認識できないため、内視鏡検査(胃カメラ)の方がこうした病変の指摘には断然優れています。また、内視鏡検査(胃カメラ)では食道がんも同様にして診断することができますが、バリウムでは食道の中はすぐに流れ去ってしまうため詳細な観察は困難です。
さらに内視鏡検査(胃カメラ)ではがんが疑われたらその病変の組織を一部採取(生検)して病理診断(顕微鏡診断)によってそのままがんかどうかの確定診断をつけることができます。バリウムではこうしたことはできないため、けっきょく後日改めて内視鏡検査(胃カメラ)も受けて確定診断を付ける必要があり、二度手間のかかる効率の悪い検査となります。それなら初めから内視鏡検査(胃カメラ)を受ければ良いのではないかと思われる方も多いのではないのでしょうか?
また、バリウム検査ではバリウムの誤嚥による肺炎や、腸にバリウムが詰まることによる腸閉塞が起こることもあり、特にご高齢の方では注意が必要です。
一方の内視鏡検査(胃カメラ)には「しんどい」というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、当院ではなるべく苦痛が少なく検査を受けて頂けるように細いカメラを使用し、鼻からの検査も可能です。また、ご希望の方には追加費用無しで麻酔(鎮静剤)を使用しております。
このように胃がん検診を受けることにより胃がんによる死亡率を低下させることが知られていますが、現在宝塚市では胃がん検診は行われておりません。また、バリウムよりも内視鏡検査(胃カメラ)の方が早期がんの発見率が高く、検査精度が高いというデータが出ています。
これらの状況を踏まえ、胃がんで亡くなる方を0にすることを目指して当院では独自に内視鏡ドック(胃カメラ検診)を行っております。詳しい内容や費用などはこちらをご覧ください。採血やレントゲンなどの含まれる一般検診や、大腸内視鏡検査(大腸カメラ)と同じ日に組み合わせて検査を行うこともできます。ご予約は予約フォームの「内視鏡ドック」(一般検診も同時にご希望される場合は「定期検診・一般検診」)のタブや、お電話でも受け付けておりますので、是非いちどご検討ください。
- 斉藤英夫ら 上部消化管検診における内視鏡検査の有用性に関する検討 健康医学 14(1):5~8, 1999
- Hosokawa O et al. Decreased death from gastric cancer by endoscopic screening: association with a population-based cancer registry. Scand J Gastroenterol 2008;43:1112-5.
このような症状が出たら―吐き気・嘔吐
カテゴリー:内科全般| 2025.06.04
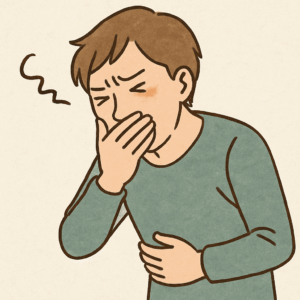 吐き気・嘔吐は飲酒や胃腸炎など、さまざまな原因で起こります。こちらでは吐き気や嘔吐が起こるメカニズムや、その原因となる病気についてご説明致します。なかには恐い病気が隠れていることもありますので、吐き気や嘔吐が続く場合は一度病院を受診されることをお勧めします。
吐き気・嘔吐は飲酒や胃腸炎など、さまざまな原因で起こります。こちらでは吐き気や嘔吐が起こるメカニズムや、その原因となる病気についてご説明致します。なかには恐い病気が隠れていることもありますので、吐き気や嘔吐が続く場合は一度病院を受診されることをお勧めします。
・嘔吐の起こる仕組み
脳の延髄というところに嘔吐中枢という領域がありますが、この嘔吐中枢が刺激されると嘔吐が起こります。嘔吐が起こるには
- 嘔吐中枢が直接刺激される場合
- 内臓から迷走神経という神経を経由して刺激される場合
- 耳の中にある器官(内耳・前庭)から刺激が伝えられる場合
- 化学物質による刺激が起こる場合
- 精神的な反応として嘔吐する場合
- 消化管の狭窄・通過障害
などがあります。従って胃腸炎など胃や腸の病気だけではなく、全身的な要素を考慮する必要があります。ここではそれぞれどのような病気が考えられるかをご説明していきます。
・吐き気・嘔吐の原因として考えられる病気
- 嘔吐中枢の直接刺激
脳腫瘍や脳出血、髄膜炎などにより頭蓋骨の中の圧力が高まると嘔吐中枢が直接刺激
され嘔吐が起こります。この場合、吐き気は伴わないことが特徴的です。頭をぶつけた少し後(血腫が大きくなるまで数時間~数ヶ月後のこともあります)に突然嘔吐し始めたり、意識障害や麻痺・激しい頭痛などの症状を伴う場合は頭のCTや髄液検査などを行う必要があります。一刻を争うこともありますので、頭の病気が疑われる場合はためらうことなく救急車を呼んで頂く必要があります。
- 内臓からの迷走神経を経由した刺激
迷走神経とは脳の延髄から出ている神経で体の中で多数枝分かれし、胸部や腹部の中の各臓器にも広く分布しています。下記の様々な病気により臓器に異常が生じると、この迷走神経を介して刺激が脳に伝わり、吐き気・嘔吐を生じることがあります。
・胃腸炎や胃・十二指腸潰瘍、虫垂炎、胃がんなどの消化管の病気
・急性肝炎・急性膵炎・胆石・胆嚢炎などの肝・胆・膵の病気
・心不全・心筋梗塞・狭心症などの心臓の病気
・尿路結石・腹膜炎など
- 耳の中にある器官(内耳・前庭)から伝わる刺激
耳の奥には内耳・前庭器官と呼ばれる平衡感覚や体の傾きを感知し、脳に伝える器官があります。この器官の異常により刺激が嘔吐中枢に伝えられると吐き気や嘔吐を生じ、乗り物酔いやメニエール病などにみられます。
- 化学物質による刺激
脳の脳幹という部分に化学受容体誘発帯(chemoreceptor trigger zone, CTZ)と呼ばれる領域があり、血液中の薬物や毒物に反応して嘔吐中枢に刺激を送ります。ニコチンなどの薬物や食中毒による毒素が血液中に貯まると嘔吐を生じます。アルコールを飲み過ぎたといきに吐いてしまうのも同じ理由です。
また、腎臓が悪くなったり、低酸素状態が続いたりすると体にとって毒になる化学物質が血液中に増加していきますので、それらもCTZへの刺激を介して嘔吐を引き起こすことがあります。
- 精神的な反応としての嘔吐
神経性、心因性の要因が嘔吐の原因となることもあります。これに属するものとしてはストレスや恐怖、ショック、抑うつ、PTSDなどによるものがあります。
- 消化管の狭窄、通過障害による嘔吐
消化管(胃腸)に狭くなっている部位があり、物理的に通過が障害されると嘔吐が起こります。胃がんや大腸がんにより狭窄が生じたり、潰瘍によって狭窄が形成されたりします。
このように吐き気や嘔吐は様々な病気が原因で起こります。胃腸炎などの感染症が原因であれば次第に治まることが多いですが、吐き気や嘔吐が続く場合は胃がんや大腸がんなどの重大な病気が隠れている場合もありますので、いちど内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)を行い詳しく調べてみることをお勧め致します。
令和7年度 予防接種について
カテゴリー:内科全般| 2025.05.15
~帯状疱疹、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌、B型肝炎ワクチンのご案内~
こんにちは。水谷内科クリニックです。
当院では、各種ワクチンを実施しております。今回は、宝塚市で新たに始まった定期接種や、現在も継続中のワクチンについてご紹介します。
予防接種で病気を防ぎましょう!
ワクチンは、重い感染症を未然に防ぐためにとても重要です。
「かかってから治療する」のではなく、「かからないように備える」ことが、これからの健康管理の基本になっています。
年齢やライフスタイルに合わせた予防接種を受けることで、ご自身はもちろん、ご家族や周りの大切な人たちも守ることができます。
ぜひこの機会に、予防接種について考えてみませんか?
当院で接種できるワクチン一覧です!
■帯状疱疹ワクチン「シングリックス®」【定期接種・任意接種】
宝塚市では、R7年度4月より帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。
・帯状疱疹は、免疫力が低下した際に発症しやすく、強い痛みを伴うことがある疾患です。
帯状疱疹ワクチンには、生ワクチン、不活化ワクチンがありますが、当院は効果の高い不活化ワクチン(シングリックス®)のみ取り扱っています。
・不活化ワクチン(シングリックス®)は2回接種が必要です。2回目は2か月以上6カ月後までの間隔で接種する必要があります。
〈定期接種の対象者〉
- 2026年4月1日時点で65歳の方
- 2026年4月1日時点で70、75、80、85、90、95、100歳以上の方
- 接種時点で60~65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害を有する人で、身体障害者手帳1級の認定を受けている方
→自己負担額11000円/回
〈任意接種助成金の対象者〉
- 接種時に満50歳以上、かつ令和8年3月31日時点で60歳以下の方(定期接種対象者以外)はこれまで通り任意接種の助成が受けられます。
→4000円/回の助成あり(助成は1回のみです)
※接種対象者や申請方法など、詳しい情報は宝塚市のホームページに掲載されています。接種ご希望の方は、
ご確認ください。
■子宮頸がんワクチン「シルガード9®」【定期接種】
宝塚市では、子宮頸がんワクチン(シルガード9®)のキャッチアップ接種が引き続き行われています。
・若い女性を中心に接種が推奨されるワクチンです。
・対象は小学6年生~高校1年生の女子です。キャッチアップ接種の新規受付は終了しましたが、2025年3月までに1回目を終了している方は、2026年3月末まで公費(無料)の対象となります。
・初回接種時の年齢に応じて、2回または3回接種が必要です。
・接種スケジュールをご確認の上、早めに接種することをお勧めします。
※母子手帳が必要になりますので、必ずご持参ください。
・定期接種の機会を逃してしまった方は、任意で接種することも可能です。
■高齢者肺炎球菌ワクチン「ニューモバックスNP®」【定期接種】
・高齢者の重症肺炎を防ぐため、宝塚市の定期接種対象者に肺炎球菌ワクチンを接種しています。
・対象は、宝塚市に住民票のある65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)です。また、60~64歳の方で、心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により身体障害者1級を持っている方も対象です。
→自己負担額4000円
※高齢者肺炎球菌定期予防接種券が必要となりますので、ご持参お願いします。
■B型肝炎ワクチン「ヘプタバックス®‐Ⅱ」【任意接種】
・血液や体液を介して感染するB型肝炎を予防するためのワクチンも実施しています。
特に、医療従事者や海外渡航者など、B型肝炎の感染のリスクが高い方に推奨されています。
・3回接種が必要です(初回、4週間後、6か月後)
→5500円/回
【最後に】
感染症から身を守るためには、予防接種がもっとも効果的な手段のひとつです。
「まだいいかな」と思っている間に、接種のタイミングを逃してしまうこともあります。
健康な今だからこそ、未来の備えをしておきましょう。
ご自身に必要なワクチンについて気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。
当院では、各種ワクチン接種を事前予約制で行っております。
ご希望の方は、早めにお問い合わせください。