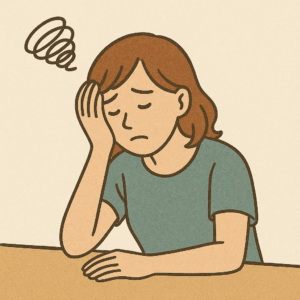バックナンバー
- 内科全般
- 内視鏡
このような症状が出たら—倦怠感
カテゴリー:内科全般| 2025.02.23
「気分がすぐれない」「だるい」「気力が無い」などの症状は「全身倦怠感」などと表現されます。
このような感覚は多かれ少なかれ病気の方のほとんどに存在するため、これだけでなんの病気であるかを判断することは難しいですが、背景に重大な病気が隠れていることもあるため、このような症状が持続する方は一度詳しく調べてみることをお勧めします。
全身倦怠感をきたす原因としては次のようなものが考えられます。
・低血圧
・貧血
・脱水状態
・風邪などの感染症
・自律神経障害
・メンタルの不調
・ホルモンの不調
・肝臓病
・腎臓病
・心不全
・糖尿病
・がん
全身倦怠感をきたすような病気は上記のように多岐にわたり、診察時に詳しく症状をお伺いしながら適切な検査を行っていきます。
低血圧や貧血、脱水などが原因の場合はふらつき・立ちくらみなどの症状を伴うことが多いです。血液検査などでこれらが疑われる場合は点滴や内服薬で治療を行っていきます。貧血が認められた場合は貧血の原因を調べることも重要です。
発熱や咳・鼻水などの症状を伴う場合は風邪などの感染症が疑われます。
自律神経障害やメンタルの不調に対しては当院では漢方薬の内服など内科的な治療を行っております。必要があれば心療内科など専門的なクリニックをご紹介致します。
甲状腺ホルモンや女性ホルモンなどのホルモンの不調でも倦怠感が出現します。エコーや血液検査などで甲状腺の形態やホルモンの分泌量を測定し、状態に合わせた治療を行っていきます。専門的な治療が必要な場合は近隣の内分泌内科や婦人科と連携致します。
肝臓は沈黙の臓器とも呼ばれており、肝臓が悪くなってもなかなか症状が出づらいですが、肝臓病が進行し肝硬変の状態となると全身倦怠感が出現します。他にも黄疸(目や体が黄色くなる)、全身のむくみ、お腹の腫れ(腹水)などが出現することがあります。黄疸は自分ではなかなか気がつかないこともあります。長らく日本では肝臓の病気といえばB型肝炎やC型肝炎などのウイルス性肝炎が多かったですが、近年では脂肪肝やアルコール性肝障害により肝硬変・肝臓がんとなる方が増えています。肥満気味の方やアルコール多飲のある方は注意が必要です。
腎臓は血液中の不要物・老廃物や過剰な水分を回収し、尿の中に排泄する仕事をしています。腎臓が悪くなると、この働きが低下し血液中に老廃物や過剰な水分が貯まって全身倦怠感・高血圧・むくみなどを引き起こします。診断のためには血液検査や尿検査・腹部エコーなどで腎臓の値、尿の状態をチェックします。
心不全があると、歩いたり動いたりするとすぐ息切れをするなどの症状が出現します。胸のレントゲンで心臓の影が大きくなっていたる、血液検査でBNPという数値が上昇している場合は心不全の可能性があります。
糖尿病でも高血糖の状態が持続すると全身倦怠感が出現することがあります。健診などで血糖値が高い、HbA1cが高いなどを言われたことがある方は一度受診されることをお勧め致します。
そして全身倦怠感の原因となる病気として重要なものとしては「がん」があります。長期間倦怠感が改善しない、体重がどんどん減っていくなどの症状が続く場合は注意が必要です。
がんが疑われる場合はレントゲンやCT・エコー、内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)などの画像検査を行い、診断をしていきます。また万が一がんが見つかった場合は、当院では宝塚市立病院・関西労災病院・兵庫医大・阪大病院など近隣のがん拠点病院と緊密に連携しておりますので、病気の状態や患者様のお住まい・ご希望に合わせて、スムーズに安心して適切な治療を受けて頂けるように責任を持って手配致します。
「体がだるい」などの症状が続く方はぜひお気軽にご相談ください。
インフルエンザの流行期に入りました!
カテゴリー:内科全般| 2024.11.08
インフルエンザは、インフルエンザウイルスが原因で引き起こされる呼吸器の感染症です。日本では例年11月~12月頃に流行が始まり、翌1~2月にかけてピークを迎えます。流行の程度やピークの時期はその年によって異なるので、これからの時期は予防を心がけることが大切です。そこで今回はインフルエンザの症状や予防対策についてお伝えします。
宝塚市内でもインフルエンザにより学級閉鎖となる学校が出始めるなど、感染の流行期に入りつつあります。
♦感染経路は?
インフルエンザウイルスは増殖のスピードが速いため感染力が非常に強く、日本では毎年約1千万人、約10人に1人が感染しているといわれています。
発症した日の前日から発症後3~7日間は感染者の鼻やのどからウイルスが排出されており、周囲の人に感染を広げるリスクがあります。
主な感染経路は、飛沫感染と接触感染です。
・飛沫感染…感染者の咳やくしゃみ、会話によって口から飛び散ったウイルスを含む小さな水滴(飛沫)を吸い込むことによる感染
・接触感染…ドアノブ、スイッチ、手すりなどを介して手にウイルスが付着し、その手で口や鼻、目などに触れることによる感染
♦もしも感染したら?
・潜伏期間と症状
インフルエンザウイルスにはいくつかの型に分けられ、流行的な広がりを見せるのはA型とB型です。
インフルエンザウイルスに感染してもすぐに症状はでません。1~3日間程度の潜伏期間の後に発熱(通常38℃以上の高熱)や頭痛、倦怠感、筋肉痛、関節痛などの症状が急激にあらわれます。これらに続いて、咳や鼻水などの症状があらわれます。
インフルエンザと通常の風邪の違いについてよくご質問がありますが、インフルエンザは風邪と比べて全身症状(急な発熱や倦怠感、食欲不振、関節痛、筋肉痛など)が強いのが特徴です。風邪の多くは咳、のどの痛み、鼻水などが中心で、発熱はインフルエンザほど高くない傾向があります。
・インフルエンザかな?と思ったら、早めに医療機関を受診しましょう
インフルエンザを疑う症状が出たら、医療機関を受診しましょう。早めの受診が望ましいですが、発熱後6~12時間未満の場合、検査を受けても結果が陽性にならないことがあります。高熱が続く、呼吸が苦しい、ぐったりしている、嘔吐や下痢が続いて水分も取れないなどの症状がみられる場合は、様子を見ずに早めに受診してください。高齢者や乳幼児、妊娠中の女性、持病のある方は重症化しやすいため、特に注意が必要です。
・治療とお薬について
インフルエンザの治療では、抗インフルエンザウイルス薬を用いることがあります。発症から48時間以内に服用すると、発熱期間を1~2日間短縮する効果と重症化を予防する効果が期待できます。ただし、服用が遅れた場合は十分な効果は期待できません。 他には、発熱に対して解熱鎮痛薬を用いたり、咳や痰がある場合にはそれらの症状を改善するお薬が用いられます。
♦インフルエンザの予防対策
感染を防ぐために、日ごろから予防対策を心がけましょう。
・流行期は混雑している場所への外出を控える
・咳が出るときや外出時はマスクを着用する(鼻とあごを覆うように)
・帰宅したらうがいと流水・石鹸による手洗いをする
・アルコール製剤を活用し手指を清潔栄養に保つ
・室内はこまめに換気し、適切な湿度(50~60%)に保つ
・十分な休養とバランスのとれた食事をとる
また予防接種には、発症をある程度抑えたり、感染しても重症化を防ぐ効果が期待されています。ご自身の発症予防はもちろん、家族間での感染拡大を防ぐためにも有効です。予防接種をしてから抗体ができ、最も効果が高くなるのは、予防接種をしてから1~2か月後です。インフルエンザのピークを迎える前の11月~12月中旬までには接種を済ませておきましょう。
♦さいごに
当院ではどなた様も安心して受診いただけるよう、発熱など症状のある患者様と一般の患者様と待合室を分けております。予約時・来院時は受付に症状をお伝えください。また、インフルエンザ迅速検査キットを用いての診断も行っております。予防接種も行っておりますので(予約制)、ご希望の方は当院までお問合せください。
胃炎について
カテゴリー:内視鏡| 2024.10.26
ひとことに胃炎と言っても様々な種類の胃炎があります。
普通の胃薬では改善が見込めず特別な治療を行わないといけないものや、逆に症状がなければ治療が必要ないものなど、その原因によって対応も様々です。
胃炎の症状
胃に炎症が起こるとみぞおち付近に痛みが出ることが多いです。また、胃の動きが悪くなることにより胃もたれが出たり、食欲がなくなったりすることもあります。出血を伴うようなひどい胃炎が起こっている場合は便が黒くなります(黒色便・タール便)。
胃炎の種類
びらん性胃炎
数mm~数cm大の発赤が散在します。発赤の中央は陥凹し、小さな白苔を伴ったり微量に出血したりすることがあります。多発することが多いですが、単発で不整形のものは胃癌との鑑別が必要です。
疣状胃炎
慢性胃炎の一種で、胃の前庭部(出口の近く)にいぼのようなびらんが多発します。歩チープ状・混紡状・数珠状などの形をとることもあり、単発のこともあります。胃がんに類似することもあり、見た目だけではがんとの区別が難しいことがあります。特にサイズが大きく、形状が不整なものは注意が必要です。
胃アミロイドーシス
胃の粘膜の下にアミロイドという物質が沈着することにより胃の表面に顆粒状の隆起やびらんがみられます。関節リウマチなどに合併することが多いです。
鳥肌胃炎
胃の出口周辺(前庭部)~中央付近(胃角部)にかけて広くみられます。3mm大の小結節状~顆粒状の隆起が均一に密集し、胃の表面が鳥肌のようにみえます。隆起の中心には陥凹した白色の斑点がみられます。ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)の感染が原因であることが多く、ピロリ菌の除菌治療が必要です。
萎縮性胃炎
こちらもピロリ菌感染が原因による胃炎です。胃の粘膜が薄くなり、粘膜の奥の血管が透けて見えます。胃のひだが萎縮したり、消失したりもします。ピロリ菌に長期間感染していると胃がんの原因となることが知られています。また、除菌治療を行うのが早ければ早いほど胃がんのリスクも低下しますので、早めに診断・治療を行う必要があります。
薬剤性胃炎
薬の副作用により胃炎を生じることがあります。
特にロキソニンなどの解熱鎮痛薬や、アスピリンなどの血液をサラサラにする薬は胃炎を生じさせやすいことがよく知られています。
これらの薬を飲むときは胃を保護するために胃薬を一緒に飲むことをお勧めすることもあります。
門脈圧亢進性胃症
肝硬変に合併する胃炎です。炎症の所見に乏しく、血流がうっ滞することにより胃の粘膜にむくみ・発赤・出血がおこります。粘膜のむくみにより胃の表面が蛇のうろこのように見えるsnakeskin apperanceや多発する点状の出血など特徴的な所見がみられます。根本的な原因は肝臓にあるため、血液検査や腹部エコーで肝臓の機能を検査し、肝臓の治療を行っていく必要があります。
好酸球性胃炎
アレルギーが原因の胃炎で腹痛を繰り返します。吸収障害により栄養不良となり、体がむくみやすくなったりすることもあります。胃だけでなく、食道や大腸にも病変が出現することがあります。重症の場合はステロイドによる治療が必要となります。
DAVE・GAVE
正式名称をびまん性前庭部毛細血管拡張症という長い名前の胃炎です。前庭部(胃の出口付近)に毛細血管の拡張が多発し、出血がみられます。出血がひどくなると便が黒くなったり(タール便)、貧血によるふらつきが出たりすることがあります。出血が持続する場合は内視鏡を用いて止血を行う必要があります。
胃梅毒
浅く、形状が不整なびらんが多発します。顆粒状の変化もあります。粘膜は鈍い光沢のある暗い赤色となり、出血しやすくなります。胃の壁が固く、内腔が狭くなることもあります。梅毒の治療を行う必要があります。
胃アニサキス症
アニサキスはサバやイカに寄生している寄生虫でこれらを生で食べることで感染することがあります。アニサキスに対するアレルギー反応で、これらを食べたあとに急激にみぞおちが痛くなります。
内視鏡検査(胃カメラ)を行うとアニサキスの虫体をみつけることができ、その場で鉗子を用いて摘出します。虫体を摘出するとお腹の痛みはすみやかに改善します。
アニサキスは冷凍すると死滅するので、対策としてはサバやイカを生で食べるときは一度冷凍すること、よく噛んで食べることなどが挙げられます。
上記のように一言で胃炎と言っても色々な胃炎があります。病気によって原因・治療はそれぞれですので、しっかりと診察を行い、内視鏡検査(胃カメラ)で特徴的な所見がないか丁寧に観察し、必要に応じて生検(病理検査)などを行いながら胃炎の診断・治療を行っています。
また、胃炎の中にはがんとの区別が難しいものもあります。まぎらわしい病変を見つけた際は、胃内に色素を散布したり、内視鏡のNBI(狭帯域光観察)という特殊な光をあてるモードを使用したりしながら丁寧に観察し、必要に応じて細胞を採取し良性か悪性かをしっかりと診断していきます。
胃炎の中には症状が出にくいものもありますが、腹痛・胃もたれ・黒色便などの症状が出るものもあります。また、ピロリ菌に感染していた場合、長期間感染が持続していると胃がんの原因になるためピロリ菌の治療を行う必要があります。ピロリ菌は飲み薬を1週間飲むだけで治療が可能です。早く治療すれば早く治療するほど胃がんになるリスクは下がりますので、心配な症状がある方は一度内視鏡検査(胃カメラ)を受けられることをお勧めします。
予防接種・ワクチンについて
カテゴリー:内科全般| 2024.09.27
~予防接種について~
10月1日よりインフルエンザ及び新型コロナワクチンの定期接種、任意接種を開始いたします。
これに伴い、当院ではインフルエンザ、新型コロナ、高齢者肺炎球菌、B型肝炎、子宮頸がん、帯状疱疹のワクチンを取り扱っております。
上記以外のワクチンについても接種可能なものもございますので、ご希望の方はお電話にてお問い合わせください。
※当院では、インフルエンザと新型コロナワクチンの同時接種は行っておりません。
予防接種を受ける前の注意事項がございますので、ご確認ください。
◇注意事項◇
◇接種前にご自宅で体温を測定し、明らかな発熱(37.5℃以上)がある場合や体調が悪い場合などは、ワクチン接種をお控えください。
また、重篤な急性疾患にかかっている方、以前ワクチン接種によりアナフィラキシーショックを引き起こした方、予防接種を行うことが不適切だと医師が判断した場合には予防接種を受けられない場合があります。
◇接種日から次の接種までの間隔をご確認ください。原則として、生ワクチンを接種した後は他の生ワクチンを接種するまでは接種後4週間(中27日)以上間隔を空ける必要があります。。BCG・MRワクチン(麻疹・風疹混合)・麻疹・風疹・水痘・ロタウイルス・流行性耳下腺炎(おたふく風邪)・黄熱病のワクチンなどが該当します。
◇当日は、診察券(受診歴のある方)、保険証またはマイナンバーカード、予診票・接種券をお持ちの方はご持参お願いします。
◇20歳以下の方は、母子手帳をご持参ください。(お忘れの場合は受けていただけませんのでご注意ください)小児の方は、医療証もご持参ください。
◇ワクチンは肩に注射しますので、Tシャツなど肩を出せる服でご来院ください。
◇待ち時間の短縮のため、以下の予防接種に関しては、あらかじめ予診票をダウンロードし、印刷・記入していただくことができます。記載後の予診票は当日お持ちください。
クリニックにて予診票をお渡しし、その場で記載して頂くことも可能です。
シルガード(子宮頸がんワクチン)
0426revised_silgard9_prechecksheet_word24.pdf (msdconnect.jp)
シングリックス(帯状疱疹ワクチン)
ニューモバックス(肺炎球菌ワクチン)
pneumococcal_polysaccharide_vaccine_inquiry_form.pdf (msdconnect.jp)
ヘプタバックス(B型肝炎ワクチン)
heptavax_prechecksheet_j_a.pdf (msdconnect.jp)
インフルエンザワクチン及びコロナワクチンの説明をさせていただきます。
- インフルエンザワクチン
インフルエンザウイルスは、毎年違う種類が流行するため、予防接種も毎年行う必要があります。日本では毎年12月~翌3月頃の間に流行します。インフルエンザワクチン1回接種による持続期間は約5カ月、そして接種後に効果がでるまでに約2週間かかると言われています。これを考慮し、10月下旬~12月頃に接種することが望ましいです。下記の定期接種対象に該当する方は宝塚市より接種代金の補助が出ます。
定期接種の対象者について(令和6年10月1日~令和7年1日31日)
・満65歳以上の宝塚市民の方
・満60~満65歳未満の人で心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害を有し、身体障害手帳1級の認定を受けている宝塚市民の方
・尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に住民票がある方で、上記に該当する場合(今年度より他市依頼書は不要です)
- 新型コロナワクチン
2024年3月までは、特例接種として自治体が指定する医療機関・接種会場にて公費(無料)で接種できていましたが、令和6年度4月以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種上の特例臨時接種から変更となり、季節性インフルエンザと同様のB類疾病の定期接種に位置づけられました。定期接種の対象に該当する方は宝塚市より接種代金の補助が出ます。
定期接種の対象者について(令和6年10月1日~令和7年1日31日)
・満65歳以上の宝塚市民の方
・満60~満65歳未満の人で心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能障害を有し、身体障害手帳1級の認定を受けている宝塚市民の方
・尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、猪名川町に住民票がある方で、上記に該当する場合(今年度より他市依頼書は不要です)
※今年度より市から配布されるクーポンや予診票はありません。
<注意事項>
・前回のコロナワクチンの接種から少なくとも3カ月経過した後に接種可能です。過去にコロナワクチン接種歴のない場合は、4週間の間隔をおいて2回目を行うことが可能です。
- 高齢者肺炎球菌ワクチン
- B型肝炎ワクチン
- 子宮頸がんワクチン
- 帯状疱疹ワクチンについて
予防接種後を受けたあとの注意事項について
◇予防接種を受けたあと30分間程度は、体調の変化に注意してください。
当院で副反応の観察をさせていただくことがあります。
◇接種した日は、普段通りの生活で構いません。ただし、激しい運動は避けましょう。過度な飲酒もお控えください。
◇接種した日の入浴は構いませんが、接種部位を強くこするのは避けましょう。
◇生ワクチンは接種4週間、不活化ワクチンは接種後1週間、副反応の出現に注意してください。
※基本的にワクチン在庫はご予約に応じ調整しておりますので、接種を希望される方は、あらかじめお電話か当院のホームページよりご予約をお願いいたします。
予約の変更、キャンセル等はお早めにご連絡お願いいたします。
肺炎球菌ワクチン
カテゴリー:内科全般| 2024.09.27
肺炎球菌ワクチン
肺炎は、日本人の死因の第5位となっています。成人の肺炎の2~3割は「肺炎球菌」という細菌により引き起こされます。この肺炎球菌が起こす肺炎の一部は予防接種で防ぐことができます。肺炎球菌には約90種類の血清型がありますが、高齢者肺炎球菌の予防接種は、その中でも成人の重症肺炎の原因となる23種類に効果があります。すべての肺炎を防ぐわけではなく、重症化を防ぐためのワクチンです。
定期接種の対象者について
・宝塚市に住民票がある65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
・60~64歳で心臓、腎臓、著しい呼吸器の機能障害・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により身体障害者手帳1級をお持ちの、宝塚市に住民票がある方
〈注意事項〉
・過去に肺炎球菌ワクチンを接種した方は定期接種の対象外となります。
また、接種歴のある方は5年間接種ができませんのでご注意ください。